
豊臣秀吉は農民の身分に生まれたにもかかわらず
天下人まで上りつめた下剋上武将やなー

秀吉殿は信長殿のもとで働いていたのも
大出世の要因じゃな

信長も時代の寵児だったもんなー
今回は豊臣秀吉の生涯をみていこう!
豊臣秀吉の年表




秀吉はたくさんの合戦を経験してきたけど
その勝率は7割を越えるよ


秀吉殿が勝利する条件を整えてから合戦に挑んだり
着実に勝利できる方法を選んだからじゃろな


だから、朝鮮出兵では思うように勝利できなかったのか


統治しやすくした。(高台寺蔵)
豊臣秀吉の相関図




秀吉は何人もの側室をもうけたけど、
1番大切にしていたのは正室のねねみたいだな


ねね殿は武家の娘じゃったから
2人の結婚は当初反対されておったんじゃよ


(高台寺所蔵)
豊臣秀吉の誕生
豊臣秀吉は1537年、木下弥右衛門と妻・仲(大政所)の子として生まれました。秀吉は15歳になった時、「侍になる」といって今川家の陪臣である松下之綱に仕えました。
そして、木下藤吉郎と名乗って、松下之綱から優遇されていました。ところが、突如出奔して織田信長に出仕します。


秀吉の幼少期については、わかっていないことが多くて
母親の再婚相手から虐待を受けていたとも


いわれている。(落合芳幾作)
農民から武士へ
織田信長に小者として仕えはじめ、清洲城の普請奉行、台所奉行などを引き受けて大きな成果をあげ、織田家内で頭角を現してゆきます。


この頃、信長の草履を懐で温めていた話は有名やなー
主君・信長の美濃攻略の際、秀吉は、川を利用して敵前で一夜にして墨俣城を築きあげました。また、観音寺城の戦いでは夜襲を仕掛けて陥落させています。
さらに、信長の最大のピンチであった金ヶ崎の退き口では、明智光秀とともに殿(最後尾)を務め功績をあげました。


金ヶ崎の退き口は、信長殿と同盟関係を結んでいた浅井長政が突如裏切ったことにより
織田軍が浅井朝倉軍に挟み撃ちにあった合戦じゃ
織田家臣団の中でも頭角を現していた秀吉は、柴田勝家と丹羽長秀から名前をもらって羽柴秀吉と改名。また、信長の命により、中国攻めを取り掛かります。兵糧攻めや水攻めなどで相手を疲弊させることで、相手を降伏させて確実に城を落としました。


(赤松之城水責之図)
天下人へ
中国攻めを行なっている最中、京都で本能寺の変が勃発し、主君の織田信長が横死してしまいます。秀吉は急いで毛利家と和解して京都に引き返し、逆賊・明智光秀を討伐しました。


これは中国大返しといわれ、10日くらいかかったみたいやな


それでもさすがの行動力じゃ
本能寺の変後、織田家の後継者を決める清洲会議が開かれました。秀吉は柴田勝家の反対意見を跳ね除けて、信長の孫・三法師を推薦します。
この会議で柴田勝家と秀吉との間で溝が生まれてしまいました。翌年、秀吉は柴田勝家と衝突し、賤ヶ岳の戦いが勃発。秀吉は柴田勝家に仕えていた前田利家を引き込み勝利をおさめます。


秀吉殿は柴田勝家を倒したことで、織田家での実権を完全に握ったんじゃ
石山本願寺の跡地に大坂城を建てられたぞ
織田家を乗っ取った秀吉は、信長と同盟を結んでいた徳川家康と衝突。小牧長久手の戦いが起こりました。この戦いにより、秀吉の家臣である森長可や池田恒興などが討ち死にしてしまいます。結局、両者は講和を結び、合戦を終結させました。


豊臣軍は兵力では徳川軍に勝っていたけど、
徳川軍は情報をかき集めて、豊臣軍の奇襲攻撃を何度も防いだぞ
秀吉は天下統一を達成するため、四国攻め、九州攻めを行いました。これらを成功させると西日本を手中におさめ、さらに関東の覇者・北条家も攻略。こうして秀吉は短期間で天下を統一したのでした。


プライドの高い生まれながらの武将は頭をなかなか下げれないんじゃが、
秀吉殿は頭を下げて頼み事ができるのも強みじゃな


出自を粉飾するため、官位を得たかった。(泉涌寺蔵)
晩年の失政、、、
小田原征伐を成功させた翌年、秀吉は関白の職を甥の豊臣秀次に譲り、自身は更なる領土拡大のため朝鮮に侵攻。最初こそ日本軍は優勢でしたが、戦が長引くにつれ劣勢となり講和を結んで終結しました。


朝鮮の水軍は強くて、日本軍の補給船が次々と壊滅してしまったんだ
秀吉と側室の淀殿の間に豊臣秀頼が生まれると、秀吉は関白となっていた豊臣秀次を目障りと思うようになっていました。そのため、秀次に謀反の疑いをかけて、切腹させています。


秀次の切腹では連帯責任として、側室や侍女までも関係者のほとんどが処刑されたんじゃ
このことで豊臣政権の支持は失墜したぞ
一度目の朝鮮出兵は講和を結んで停戦していましたが、秀吉は再び朝鮮へ侵攻。ところが、秀吉が病死してしまったために、日本軍は撤退して終結。
二度に渡る朝鮮出兵では、出費がかさんでしまったにも関わらず領地を得られませんでした。その結果豊臣政権は疲弊し、実際に出陣していた加藤清正らの武断派と秀吉の側で仕えていた石田三成ら文治派の対立が激化してしまいました。


秀吉殿の死後、朝鮮出兵に出陣していなかったわしが、天下取りに動き始めるんじゃ


釜茹での刑に処された。(陽斎豊国)
まとめ
豊臣秀吉は百姓に生まれながら、持ち前の明るさと人たらしで天下人にまでのぼりつめた武将。天下人の階段を一歩、また一歩と駆け上がるさなかの秀吉は、光のベールをまとうがの如く神々しい姿でした。しかし、これ以上ないほどの地位に登りつめたときに、秀吉は巨大な虚無感に襲われたのか、晩年は失政が目立ってしまいました。


秀吉の辞世の句は、「露と落露と消えにし我が身かな、浪速のことも夢のまた夢」





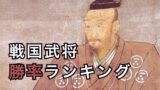









コメント
学生です。歴史の勉強のために参考にさせていただきました!吹き出しやイラスト、年表などでわかりやすくまとめられていてとっても役に立ちました!ありがとうございます。また参考にさせていただきます!