
戦国時代に主君の右腕として
戦術のサポートをしたのが軍師!

もともとは占いによって合戦の吉凶を占うのが軍師の役割じゃったが
戦国時代には戦術や外交交渉する役割となったんじゃ

今回は戦国時代に活躍した軍師をランキング形式で紹介していきます!
第10位
安国寺恵瓊
安国寺恵瓊は毛利家の外交僧。武士の家に生まれましたが、幼くして滅亡してしまったため寺の子となっていました。しかし、恵瓊の野心は大きかったため、しだいに寺内で頭角を表し京都の東福寺の僧となります。これでも恵瓊の野心は収まらず、高僧に紹介され、毛利家の外交僧となります。


恵瓊はとにかく口がうまかったから外交僧にまで上り詰めれたんだ
毛利家の外交僧となった恵瓊は当時、織田信長のもとで頭角を表していた豊臣秀吉の実力を見抜きました。その際、「信長はあと3、5年の内に横死し、藤吉郎秀吉が台頭する」と予言しています。そして秀吉の天下が決まると、ますます豊臣家に出入りするようになり、ついに城持ちの大名までに出世を果たしました。


(月岡芳年)
第9位
片倉小十郎
片倉小十郎は伊達政宗の腹心。小十郎の忠誠心は凄まじかったようで、小十郎は政宗よりも10歳も年上にも関わらず、「主君よりも先に男児を授かってはならない」と生まれてきた長男を殺害しようとしました。これにはさすがの政宗も驚き止めに入ったため、生まれたばかりの長男は助かりました。


他にも小十郎は疱瘡で飛び出た政宗の目をえぐり取ったことも
また、政宗は若くして奥州の覇者となりましたが、天下人となった豊臣秀吉には力が及びませんでした。それでも依然として、政宗を中心に伊達家内には豊臣家への抗戦派が存在していました。このときに小十郎は政宗の機嫌をとりつつ秀吉に従うことを提案。政宗は小十郎の熱心な意見を受け入れて秀吉に従順しました。


小田原征伐のときの話じゃ
このときに抗戦していたら敗れておったじゃろな


政宗との関係を重視して断った。(仙台市博物館所蔵)
第8位
直江兼続
直江兼続は上杉景勝の右腕。景勝から絶大な信頼を得ており、上杉家内で大きな権力を握っていました。そのため、当主の上杉景勝を「お館様」、直江兼続は「旦那」と呼ばれる二頭政治が敷かれました。


景勝と兼続は幼馴染じゃな
兼続は上杉家と豊臣家の取次ぎを担当し、内政面で上杉家を支えました。関ヶ原の戦いでは、盟友の石田三成とともに徳川家康に対抗。ところが、西軍が敗れてしまったため、上杉家の領土が120万石から30万石へ大幅に減封されてしまいます。それでも兼続は家臣は大事だといって、1人の家臣もリストラしませんでした。


このせいで上杉家は深刻な財政難となってしまったんです、、、


米どころと知られるのは兼続のおかげ。
(米沢市上杉博物館蔵)
第7位
小早川隆景
小早川隆景は毛利元就の三男であり、兄の吉川元春とともに甥の毛利輝元を支えた毛利両川の1人。小早川隆景は本能寺の変の際に京都へ向かって急いで戻る豊臣秀吉の軍を追撃しないように毛利家中に戒めています。
その後、頭角を表した秀吉に接近して、信頼を得ていました。そのことで、秀吉から小早川秀秋を毛利家の養子に勧められましたが、隆景は無能な秀秋が毛利家を潰しかねないと考えて、小早川家の養子としました。


隆景は五大老の候補に上がるほどの実力者でもあったんだよな


(米山寺蔵)
第6位
石田三成
石田三成は豊臣秀吉の右腕。三成は武将としては珍しく、合戦面ではなく内政面で活躍。有名な太閤検地や刀狩りは三成の指導のもと行われています。


検地は江戸時代にも引き継がれるんじゃ
また、三成の豊臣への忠誠心は武将の中でも群を抜いていました。そのせいで、少し頭が凝り固まってしまい、加藤清正や福島正則といった武将と仲違いしてしまうことも多々ありました。


三成は嫌われ者と思われがちだけど
三成と仲が良かった武将もいるよ


(東京大学史料編纂所所蔵)
第5位
豊臣秀長
豊臣秀長は豊臣秀吉の実の弟。農民上がりの秀吉には信頼できる譜代の家臣がいなかったため、血の繋がった秀長は重用されました。また、秀長は豊臣の家臣と秀吉の間をうまくとりもったため、豊臣家臣にも大変信頼されていました。


秀長が先に亡くなってしまったから
抑えが効かなくなった秀吉は暴君化してしまったとか


(春岳院所蔵)
第4位
太田道灌
太田道灌は扇谷上杉の軍師。戦国時代が始まったころ、道灌は関東地方で活躍しました。道灌が当主となった時、主君の扇谷上杉は山内上杉に比べると実力が劣っていました。道灌は今川家内での家督争いの仲裁を行い、反乱を起こしていた長尾景春を説得し、主君の上杉家と古河公方との間で和睦を成立させました。このことで、扇谷上杉の地位は一気に上がり、山内上杉と肩を並べるほどの実力にまで成長しました。


でも、太田道灌が天才すぎたから
実力を恐れた主君は道灌を殺害してしまったんだ


実力のあるものは命を狙われるからの


第3位
立花道雪
立花道雪は大友宗麟の軍師。道雪は家督を継いだ14歳のときから合戦で手柄をあげて、主君に変わって総大将として兵を指揮することもありました。主君の宗麟は弟の塩市丸と家督のことで揉めていましたが、道雪は弟と弟派の家臣を徹底的に討伐して、宗麟を当主に仕立ています。


道雪は雷を断ち切ったこともあるほどの猛将だな
また、主君の大友宗麟は酒と女に溺れることが多かったため、道雪は物おじせずにズバズバと主君にものを申して諫めたといいます。一方、家臣には優しく接しており、深い絆で結ばれていました。


道雪亡き後の大友家は急速に衰退してしもうた


立花宗茂の養父。(福厳寺所蔵)
第2位
太原雪斎
太原雪斎は今川義元の軍師。今川義元が幼い頃、京都の寺に預けられていた時から家庭教師として、義元に仕えていました。雪斎は義元が当主となれるように尽力し、義元の兄の玄広恵探を家督争いの末に葬りさっています。


太原雪斎は京都の僧だったのに
義元の養育者となることで力をつけていったんだな
また、今川家を安定させるため、武田信玄、北条氏康との間で甲相駿三国同盟を締結させています。雪斎がなくなってしまうと、義元は織田信長に桶狭間の戦いで敗れ、今川家は急速に衰退してしまいました。


今川家は太原雪斎の手腕で繁栄していたのかもしれんのー


(臨済寺)
第1位
黒田官兵衛
黒田官兵衛は豊臣秀吉に恐れられるほどの天才軍師。秀吉が織田信長の家臣であったときの中国征伐の時から軍師として活躍し、味方の損害を最小限とする兵糧攻めを得意としました。また、外交交渉や城作りも得意としており、戦国最強の軍師にふさわしい武将です。


合戦では徹底的に根回しを行なって
味方に勝利をもたらしたんじゃ
豊臣秀吉は実力のある黒田官兵衛を恐れていました。ある時、秀吉の家臣が「なぜ黒田殿には10万石程度しか与えないのですか?」と尋ねると秀吉は「お前はやつの真の力量を分かっていない。やつに100万石を与えたならば途端に天下を奪ってしまう」と答えたそうです。
官兵衛は秀吉に恐れられていたことを自覚していたのか、豊臣政権下では野心を隠していましたが、関ヶ原の戦いになるとへそくりをはたいて兵を集めました。そして、九州から天下を狙おうと意気込むも、関ヶ原の戦いが思ったよりも早く決着がついてしまい、その夢は儚く消えてしまいました。


小早川秀秋の裏切り工作をしたのが息子の黒田長政という皮肉、、、


親交があるほど、心の広い人物。(崇福寺蔵)

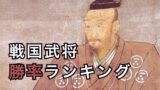















コメント